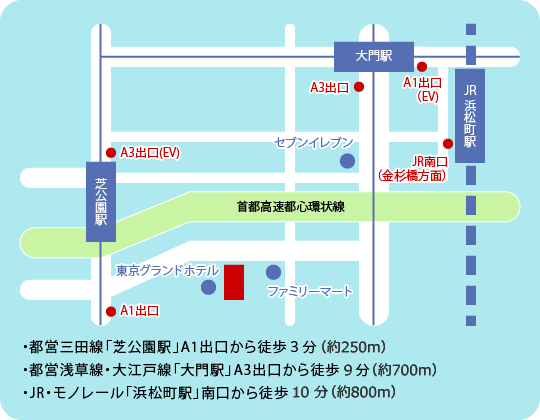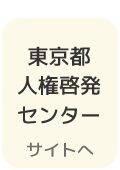本文
「現代アイヌの肖像」スペシャルコンテンツ(2)

川上 容子(1977年生まれ/帯広市出身/札幌市在住/歌手・カレー屋)
取材日:2021年8月25日
写真とインタビュー:池田 宏
インタビュー構成:浅原 裕久

── 歌をうたうのは昔から好きでしたか?
そうですね。私、小5のとき、ものまねオーディションを受けたんですよ。テレビで「ものまね王座決定戦」とかやってたの知ってます?
── コロッケやビジーフォーが出てた。
そうそう、それの素人のほう(「発表!日本ものまね大賞」)。素人が出演して優勝したらものまねタレントになれる。私は落ちましたけどね、予選で。
── 何をうたったんですか?
いっぱいうたいました。工藤静香に南野陽子、ひとりでウィンク(笑)、荻野目洋子。なんかもうそのへんの流行ってた人たち。中森明菜も。
── それは自分から出たいと。
そう。ものまね歌手になりたかった。
── アイドルとかではなく、ものまね歌手になりたかったんですね。
うん、ものまねができたんですよ。できたっていうか、みんなにうまいって言われて、自分でも似てると思ったし。でも、親にオーディション受けるって言ったら「家族の前でちゃんとできたら受けてもいいよ」って言われて、ちゃんとやって、「じゃあ、いいよ」って札幌まで連れてってくれたんです。
── いいですね(笑)。家族の前では何をうたったんですか?
全部うたった。
──いちばん得意なのは何ですか?
工藤静香(笑)。工藤静香がいちばん好きだったし、流行ってたんですよ。このあいだも、去年の5月かな、札幌のNHKの生放送に出たんですよね。「ひるまえナマら!北海道」っていう番組。そこで工藤静香のものまねしたんですよ(笑)。♪あ~らしを~ってやつ。「嵐の素顔」を。
── 最近もやってるじゃないですか(笑)。
家に録画がありますよ(笑)。

── カレー屋さんをやろうと思うようになったのは、いつごろから?
子ども産んでからですけど、ずっとカレー屋をやりたくて。シケㇾベ(キハダの実)カレーというメニューまで決めてたんです。
── シケㇾベを使ったアイヌ料理ありますよね。ラタㇱケㇷ゚(注1)とか。
私、甘いのが苦手で。
── ラタㇱケㇷ゚は甘いんですか。実は食べたことがなくて。
カボチャを甘く煮るので。
あと、子どものころは風邪をひくとシケㇾベ茶を飲まされてました。ヤカンにお水とシケㇾベを入れて、うちは薪ストーブだったので、その上に置いて煮出すんです。それに砂糖をたっぷり入れたのをおばあちゃんに飲まされて。
── おいしくないんですか?
むちゃくちゃ嫌いでした(笑)。けっこうトラウマになってる人がいるんじゃないかな?
だから、シケㇾベは甘いのとセットだと思ってました。ラタㇱケㇷ゚もそうだし、ふきの甘露煮にもシケㇾベを入れていて。
大人になってから、薄めに煎じて砂糖を入れないシケㇾベ茶を飲んで、シケㇾベ自体が嫌いなんじゃなかったんだとわかりました。
── シケㇾベを使うようになるのには、何かきっかけがあったんですか?
私、お母さんの友達のおばさんの家に行ってマッサージしてたんですよ。で、ご飯食べて行きなって言われて。そしたら肉じゃがにシケㇾベが入っていて、おいしい!ってなって。
── そのおばさんもアイヌの人ですか?
そうです。もう亡くなっちゃったんですけどね。帯広の人。肉じゃがとか、しょっぱいのには合うのがわかって、じゃあ、カレーに入れたらいいんじゃない? って思って。なんかシケㇾベって見た目が胡椒のホールに似てるじゃないですか。だからカレーに合うような気がしたんです。それでスープカレーに入れて見たらおいしくて。それで5年ぐらい前だったかな、カムイノミに持っていったんです。みんなに食べてもらったら、「お店出せるよ!」って褒められて。あとは、「二日酔いが治った」とか。
── 二日酔いに効くカレー(笑)。シケㇾベ自体がそういう効き目があるのかもしれないですね。
うちの夫は、胃が痛いときにシケㇾベを乾燥したまま2〜3粒食べて、治らなかったら6粒くらい食べてます。
── こないだ山道康子(注2)さんの家に寄らせていただいたときに、ちょっと胃がむかむかしたんです。そしたら「ちょっと待ってれ」って言われて、シケㇾベくれるのかなと思ったら、ふつうの錠剤を渡されました(笑)。
いま、シケㇾベの実がないみたいで。なんか雌が少ないらしいんですよね。
── 雌?
雌。実がなるほう。お父さんが林業で働いてるんですけど、「二風谷、実がついている木がぜんぜんない」って言ってました。前あったところに見に行ってもなかったって。雄はあるそうで、皮をもらったりはしたんですが。
── きっと内地の人に「シケㇾベ」って言ってもわからないですよね。
「キハダ」って言ったらわかります? 染料に使ってるらしいですね。染料としてお店で袋500円だったのを夫が買ってきて、煎じて飲んでました。
── むちゃくちゃ苦くないですか?
むっちゃくちゃ苦いです。
── また山道さんところの話になりますけど、「お茶飲むか?」って言われて、薪ストーブでコトコトやってるのを飲ませてくれたんですが、それがハンノキのお茶だったんです。
ハンノキってお茶にできるんだ!
── 鉄分が豊富らしいです。赤いお茶で、すごくおいしかったんですよ。しかも飲みやすくて。次にキハダのお茶も出してくれたんですが、とてもじゃなくて。
けっこう濃かったんですか?
── いや、濃いか薄いかもわかんなくて(笑)。
すごい苦いですよね。
── でもシケㇾベが採れなくなっているのは問題ですね。
北大のは大きい木なのでたくさん採れますけど、若い木だと隔年しか実がならないんですよね。私がお願いして採らせてもらっているところも毎年じゃなくて。しかも今年、すごい嵐の日があって、それでだいぶ枝が折れちゃって。
── シケㇾベは、いつごろ採れるんですか?
秋から採れるんですけど、真冬に採る人もいますね。秋に採ったらぷっくりしてます。それを乾燥させる。

── 料理は昔から好きなんですか?
お母さんがいない日とかは、姉と一緒にごはんをつくってました。好きってわけじゃないですけど。うちの姉は中学生のときに、通常の倍の量のタマネギを炒めて入れるとおいしいカレーになるのを誰かから聞いたらしくて、それをつくって、「めっちゃ、おいしい」って言って食べてたんですよね。でも、私にはくれないんです(笑)。自分のぶんだけつくって。「ひと口ちょうだい」って言ってもくれなくて。
── えっ、なんで? ふつうカレーは1人前だけつくったりしないじゃないですか。
そういう人だったんですよ。それで姉がいないあいだに食べたらめっちゃおいしくて。
── ははは。何歳差なんですか?
年子。ひどい姉だったんですよ(笑)。
── きょうだいはふたりですか?
弟もいます。弟は東京にいます。6歳離れていて、38とか。
── 子どもが料理をつくらなきゃいけないことがよくあったんですね。
ありましたね。毎年10月のマリモ祭りのときは親がいないし。
── マリモ祭りにはついていかなかった?
小学校まではついていったけど、中学校なってからは。あとは、保存会(注3)で5日間九州に行ったり。
── 保存会でそんな遠征をしてたんですか?
はい。オーストラリアにも行ってたし。
──家庭で、アイヌ料理を食べたりはしてたんですか?
食べてましたね。それこそポネオハウ(注4)がめちゃめちゃ大好きで、きょうだいみんな。弟が保育園で「いちばん好きな食べ物なあに?」て聞かれて、「骨のおつゆ」って答えたらしいんですよ。で、家庭訪問で来た先生に「骨のおつゆってなんですか?」って聞かれて(笑)、お母さんめっちゃ困って。うちがアイヌだとか、おおっぴらには言ってなかったから。
── たしかに骨のおつゆって言われてもわかんないか。骨は豚骨ですよね?
そうです。昔、いまもあるんですけど、帯広に豚肉の工場ができたんです。それで豚骨がすごい安いから、みんなアイヌの人が買って、それでオハウをつくりだしたって。
── 具材は?
家庭によって違うんです。本当に骨だけのおうちもあるし。
── ポネオハウは、肉がついた骨も一緒に入れるんでしたっけ?
肉がついた骨も煮込んで、その肉を食べるんです。骨髄が入ってたらアタリで、中身をほじって食べるのがいちばんおいしい。ツゥルツゥルなんです。材料は安いけど、時間がかかるからそんなに頻繁にはつくってはもらえなかった。だから、たまぁにつくってくれると、イェーイ! みたいな(笑)。よその家でつくったら、お母さんは呼ばれて食べに行ってました。うちは塩味だったんですけど、誰かんちで味噌を入れたのを食べたらおいしかったそうで、うちもそうしたことがありました。それにうどんを入れて食べたり。
── 聞いててお腹が減ってきました。
あとは豚の筋肉を煮て、細かく刻んでネギと一緒に食べてました。それはずっとアイヌ料理だと思ってたんですけど、うちの父さんが飯場のメシだって。
── お母さんは帯広の出身ですよね。お父さんは?
青森。父方のおじいちゃんが、ついこのあいだ亡くなりました。でも、コロナの影響で葬式にも行けないし。入院中も誰もお見舞いに行けなくて、リモートお見舞いみたいな。
── ご両親はお元気なんですね?
元気です。
── 母方がアイヌの家系で。
そうです。
── 生まれも育ちも帯広ですか?
はい。高校まで。
── 大空団地(注5)ではなく?
大空ではないんです。
── これまで帯広の話を聞かせていただいたのは、大空に生まれたか、大空にいたことがあるアイヌの方が多くて。
フシココタン(注6)があった場所なんですよ、うちがあるところが。みんなは、もともとそこに住んでた。けど、大空に行ったじゃないですか。だからフシココタンの跡に住んでいるアイヌはあまりいなくって。何軒とか。
── 子どものころ、踊りとか、アイヌの活動に関わってましたか?
関わってないです。
── 家族で保存会に入っていたのは、お母さんだけ?
そう。母は保存会でいろんなところに行ってたけど、私は観にもあんまり行ってなかった。お祭りでも、踊りのところには行かなかった。子どもは誰も踊ってなかったと思う。うちらの年代は。
── さっき、中学生になるとマリモ祭りには行かなくなったとおっしゃってましたけど、それは思春期特有の感覚で。
そうですね。親と一緒に歩いているところを見られるのも恥ずかしいっていう。一緒に行動をしなかった。
── 自分がアイヌだと知ったのがいつだったか覚えてますか?
それはね、中1。
── それまでは?
踊りは、お母さんの趣味だと思ってたの。聞いてから、そりゃそうだよな! って。顔が違うよなって。毛深いとか、彫りが深いとかは気づいてたんですけど、お母さんが、親戚って言ってたから。
── 誰のことを?
アイヌたちのことを。「アイヌの集まり」と言わないで、「親戚の集まり」って言ってたから。みんな親戚で、いろんなところに行くのも集団行動していると思ってたんです。だから、親戚ってみんな多いものだと思ってて。実際、本当の親戚もいるし。保存会の新年会が毎年あるんですけど、冬休みの宿題で「親戚みんなで温泉に行って新年会しました」とか書いてた(笑)。当時のウタリ協会(注7)とか、すごい集まりがよくて100人くらいいる。
── 中学1年生のときに知ったのは親から?
お母さんから。家にいるとき、姉と一緒に呼ばれて。私はそのとき初めて知ったんだけど、姉はアイヌだってことに気づいていたみたい。でも、姉も初めて知ったふりをしていた。
── なんて言われたんですか?
「あんたたち、アイヌなんだよ」って言われて。ガーンって。
── ガーンなんですね。
だって、小学校のときからアイヌ、アイヌっていじめられてたから。私、「アイヌ」って言葉は、ただの悪口だと思ってたんです。「バーカ」みたいな。現実に存在する人だと知らなかったんですよ。毎日のように喧嘩してたけど、それがほんとのことだったんだって思って。
言われた日の夜にお姉ちゃんとふたりで、知り合いのなかで誰がアイヌなんだろうねって話をして。それで、お母さんが「親戚」と言っていた人たちは全員アイヌなんだって気づいた。
── アイヌだと知って何か変わりましたか?
性格がガラッと変わりました。それまでは勝気で、小学校のときは学習発表会で主役やったり、児童会の議長に立候補したりしてたんですけど、そういうのがなくなったんです。前に出ちゃいけないと思って。中学生のときは本当の自分の性格を出せなくて。部活も頑張るし、ちゃんとやってはいるんだけど。
── 部活は何をしてたんですか?
剣道。
── あっ、同じですね。
えっ! ほんとですか。
── 高校のときは友達にアイヌのことを言わず?
言わないけど、わかるじゃないですか。1年生のとき、すごい嫌な感じの子がいて、ひどいことを言われたり、その親にめっちゃ遠吠えされたりして。
── 遠吠え?
犬の遠吠えをわざとするんですよ、親が。
──そんな大人がいるんですか?
そう。でもクラス変えでそいつとは離れて、2年生と3年生は楽しい高校生活で。
── そこから、いまのように歌手として表に立つようになるのには、何か転機があったんですか?
20歳くらいのときに安東ウメ子(注8)さんの歌を聞いて、うたいたい! って思ったんですよ。初めてアイヌに興味をもった。だけど、最初は言えなかったですね。自分がアイヌってことを。私をアイヌと知らずに、アイヌを馬鹿にする発言って、ふつうの性格がいい友達でもするから。私が打ち明けることでその人が後ろめたくならないかなって思った。
でも、22歳から音楽活動を始めて、30歳でアイヌの歌をうたいだして、友達がライブに来てくれるようになったら、そういうのも全部なかったことにした。歌をうたって、歌を聴いて、歌についてふつうに喋れるようになったんですよ。

── 最後にお聞きしたいのは子育てのことなんです。ご自身が育った帯広の環境と、いまお子さんふたりがいる札幌の環境は……。
全然違う。札幌が都会だからなのか、時代が違うのか。でも下の子の友達で、アイヌのことを馬鹿にする子がひとりだけいるんです。だから先生に言ったんです。お母さんにも言いました。だけど、あんまり言ったらかわいそうって思うと、それ以上言えなくなって。それで、いまだに続いてる。だけど、うちらが子どものときに比べたらよくなってるし。帯広がひどかったのかなって思ったり。
── お子さんにはアイヌのことを伝えているんですか?
伝えてて、上の子は「俺、アイヌ」って言ってます。1年生のときの担任の先生とはそういういろんなことを話してたし、クラスの子たちも息子がアイヌだと知ってたんです。ところが2年生の終わりからコロナがあって学校に行けなくなり、そのまま3年生でクラス替えがあって、新しい担任の先生にそういうことを伝えそびれてたんです。だからクラスのみんなも知らなくて。で、授業でアイヌの話が出たときに、息子が「ハーイ!」って手を挙げたんですって。なんで手を挙げてるの?ってなるじゃないですか。「もしかしてアイヌなの?」って聞かれて、「そうです!」って答えたって。
── お子さんのことを原田公久枝(注9)さんの「RUYKA ITAK」(注10)に寄せたコラムに書かれていたじゃないですか。あれは保育園のころの話ですか?
そうです。年長のひとつ前の年中。5歳ですね。私と夫が茶の間にいたら、息子が洗面所から泣きながら出てきたんです。顔から血を出して。「どうしたの!?」って聞いたら、「ひげ生えてるって馬鹿にされるから、剃ろうと思った」って。夫の剃刀を黙って使って。
── 自分の子どもが近い年齢なので余計に身につまされるというか……。
その次の年、息子が年長になってから、私がアイヌのことで取材を受けて新聞におっきく写真が載ったんです。そしたら、息子がアイヌだと知られたみたいで、「アイヌって何?」って子どもたちが聞くじゃない。そのとき、先生が息子のことを「特別なんだよ」って言ってくれたそうです。「特別」っていうのも微妙ですけど、息子はそれがうれしかったみたい。毛のこと以外は誇りをもってるんですよね。だけど、「特別」なのを悪いほうに捉える子もいるんじゃないかと心配にはなった。だから「アイヌっていじめられたら絶対言いなさいよ」とか、そういう話は息子にしました。
── 容子さんはアイヌのことでいじめられたときに親に言いましたか?
絶対に言わなかった。
── お子さんがアイヌをプラスに考えられているのならよかった。
まあ、成長するなかで、アイヌから離れたいっていう時期もあると思うんだけど、いまは誇りに感じている。あと、オリンピックで踊った(注11)のもプラスに。それと、ウポポイが話題になってるのもいいみたいですね。やっぱり、アイヌが注目される存在なのがうれしいんじゃないですかね。うちらほど複雑な思いもないだろうし。

注
(注1)ラタㇱケㇷ゚:カボチャや豆などを煮てつくるアイヌ料理。
(注2)山道康子:1946年生まれ、平取町川向出身、平取町二風谷在住。1979年に「沙流川を守る会」を立ちあげ、二風谷ダムと平取ダムの建設反対運動をおこなう。1989年にアイヌ語学校を設立。また、同年8月よりアイヌモシリ一万年祭を開催している。
(注3)保存会:帯広カムイトウウポポ保存会のこと。アイヌの歌謡や舞踊、儀式の伝承保存活動をおこなう。前身の「十勝アイヌウポポ愛好会」を1964年に改称。84年に国の重要無形⺠俗文化財に指定された。また、2021年度の文化庁長官表彰に酒井奈々子会長が選ばれている。
(注4)ポネオハウ:豚骨(ポネ)を使ったアイヌの家庭料理。汁ものをアイヌ語で「オハウ」という。
(注5)大空団地:大空団地は帯広市の人口増加に伴い、市中心部から南西に約8キロ離れたエリアで建設された人口1万人規模の集合住宅群。1967年に造成が始まり、70年に完成した。市内と周辺地域に暮らしていたアイヌの多くが移り住んだため、かつては「アイヌ団地」と呼ばれていたという。現在はバリアフリーに対応した住居への建て替えがおこなわれている.。
(注6)フシココタン:帯広市の川北地区から西帯広にかけて存在したアイヌの集落。「コタン」はアイヌ語で集落の意。
(注7)ウタリ協会:1946年に設立された北海道アイヌ協会は、1961年に組織名を北海道ウタリ協会に改称した。「アイヌ」を「ウタリ」に変えた理由は、会員の勧誘および入会時の心理的な負担を軽減するためだったという(「ウタリ」はアイヌ語で「同胞」「仲間」の意)。その後、2009年に北海道アイヌ協会に再度改称して現在に至る。
(注8)安東ウメ子:ムックリ(口琴)とウポポ(歌)の第一人者。1932年、帯広のフシココタンに生まれ、のちに幕別町千住で暮らす。帯広カムイトウウポポ保存会の設立に携わり、幕別でもマクウンベツアイヌ文化保存会(現・マクンベツアイヌ文化伝承保存会)の結成に寄与、アイヌ文化の伝承・保存、後継者の育成にあたる。2004年没。
(注9)原田公久枝:1967年生まれ、芽室町出身。幼少時より、帯広カムイトウウポポ保存会にて祖母の加藤なみえらからアイヌの歌と踊りを習う。現在は、パートをしながらアイヌの活動をおこなう。十勝アイヌの歌と踊りを伝承するユニット、フンペシスターズのメンバーでもある。
(注10)「RUYKA ITAK」:さまざまな生きづらさを抱える人たちが思いを綴り、つながるための場として、2020年6月より発行されているフリーペーパー。代表は原田公久枝。
(注11)オリンピックで踊った:当初検討されていた開会式でのアイヌの古式舞踊の披露は2020年2月に不採用が決定した。式の総合演出を統括する狂言師の野村萬斎は、「式典の制約のなかで、はまらなかった」とコメントを残している。紆余曲折の末、アイヌの舞踊はマラソン・競歩の発着点となる札幌市の大通公園で2021年8月5日〜8日に披露された。
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Plaza. All rights reserved.