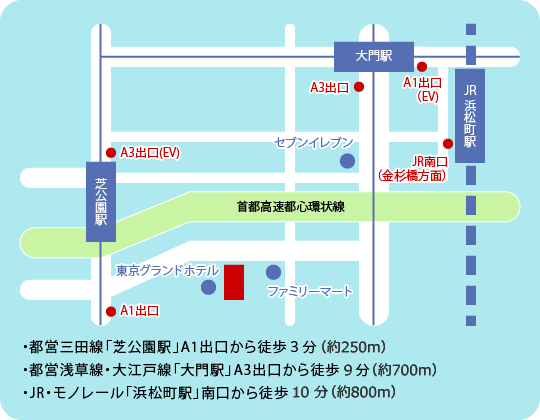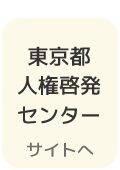本文
「現代アイヌの肖像」スペシャルコンテンツ(1)

「現代アイヌの肖像」が私たちに問いかけるもの
2022年3月11日
林 勝一(東京都人権プラザ専門員)
誰もが誇りをもって生きられる社会に向けて
私たちは誰でも尊厳が守られ、自由に幸せを追い求めることができる人権が保障されているはずです。しかし、現代の日本において、アイヌであるというだけで偏見に満ちた誹謗・中傷、嘲笑にさらされ尊厳を深く傷つけられている人々がいます。
誰もが誇りをもって生きられる社会をめざして、東京都人権プラザでは写真家・池田宏さんの写真展「現代アイヌの肖像」を開催します。

Photo:写真集『Ainu』と展覧会チラシ
アイヌへの偏見を生むもの
アイヌといえば何をイメージするでしょうか。最近ではマンガ『ゴールデンカムイ』のヒットや北海道の白老に国立施設「ウポポイ(民族共生象徴空間)」が2020年7月に開館するなど、メディアで話題になることも多くなりました。
しかし、東京都が発行する『みんなの人権』(注1)にはアイヌについて次のように解説されています。
「アイヌの人々は、生活の基盤や独自の文化を失い、いわれのない差別の中で貧困にあえいできました。アイヌの人々に対する誤った認識などから、今なお差別や偏見は残っています」。
なぜアイヌの人たちの生活の基盤や独自の文化が奪われ、差別が続いているのでしょうか。
そこには明治以降の同化政策の歴史が影響しています。例えば、女性の刺青(いれずみ)や男性の耳飾り、サケやマスを川でとること、毒矢での鹿猟などが禁じられました。また、日本語の学習が奨励され、学校ではアイヌ語が教えられませんでした。こうした同化政策によってアイヌの文化や生活は大きな打撃を受けました(注2)。
こうしたアイヌの歴史とその独自の言語や文化について十分に理解されていないことが「アイヌは過去の民族」「アイヌは北海道の問題」といった誤った認識と偏見を生み出している一因といえます。ではなぜアイヌへの理解が進まないのでしょうか。

Photo:東京都人権プラザ「アイヌの文化と伝統を理解するために」
「無自覚の特権」に気づくこと
東京都が1999年に実施した「人権に関する世論調査」(注3)で人権侵害が存在すると思うかどうかを聞いた質問に対して、「アイヌの人々」について人権侵害が「存在しない」「分からない」と答えた人の合計は60.2%で、8つの人権課題のうちでもっとも高い結果となりました。また2020年度に行われた「人権に関する都民の意識調査」(注4)において、関心がある人権課題を聞いた質問に対して「アイヌの人々の人権」と回答した人は15.7%にとどまっています。
実際には東京には多くのアイヌの人たちが暮らしていますが、これらの調査は、アイヌの問題について、関心を持っていない人が多いことを示しているといえます。
では、アイヌに関わる差別問題は自分とは「関係ない」ことなのでしょうか。この問いに対しては、札幌大学教授の本田優子さんの次の視点が参考になります。「私たちは日本語を母語として当たり前のように話すことができるのに、アイヌの人たちはそれができない状況が続いている。享受している権利が全く違うのです。私たちはこの〈無自覚の特権〉に気づかないといけません」。(注5)
かつて、関東ウタリ会の丸子美記子さんから「わたしたちはアイヌ語で子守唄を唄ってあげることができない」と言われたことを思い出します。丸子さんのこの言葉は、「母語で子守唄を唄う」という当たり前のことを奪われている人たちがいる一方で、マジョリティが無自覚に享受している特権があることを気づかせてくれます。
肖像と一人一人の語り
本展は池田さんが2019年に刊行した写真集『Ainu』(リトルモア)以降に撮り下ろされた作品20点と、被写体となったアイヌの人たち21名への池田さんによるインタビューパネルによって構成されています。
インタビューで語られる生い立ち、家族そして仕事のことなどから、直接的、間接的にアイヌというルーツがもたらしたものが浮かび上がってきます。それが差別経験など厳しい事情であればあるほど、聞かれれば誰にでも話せるようなことではないはずです。
ましてや、アイヌの存在を否定したり、誹謗・中傷したり、嘲笑することがインターネットをはじめとしたメディア空間で広がる現在の社会状況においては、実名でアイヌであることを語り、自らの「肖像」が公の場で展示されることにはリスクが伴います。アイヌに限らず今の日本社会には、自らのルーツを語ることで差別の恐怖にさらされる人たちがいることを省みなければなりません。

Photo:池田宏写真展「現代アイヌの肖像」
「現代アイヌの肖像」との出会いがもたらすもの
20点の肖像写真とそのライフストーリーのなかには、悲しく痛ましい話にとどまらないそれぞれの人生の喜びや楽しみ、そして誇りが表れています。
池田さんが捉えた「現代アイヌの肖像」は、見る者に「無自覚の特権」を自覚させ、その背後にある同化政策の歴史を省みることの先に、誇りをもって生きる一人ひとりの人間の姿との出会いをもたらしてくれるはずです。見る者が、池田さんの10年以上にわたる足跡をトレースしながらアイヌに出会い、その後もアイヌの人々との出会いを丁寧に積み重ねていくことによって、すべての人の尊厳が守られ共に生きる社会のあり方について考える機会となることを願っています。
【参考】情報誌「TOKYO人権」のアイヌ関連記事
- (1)宇梶 剛士さんインタビュー「「違い」は「彩り」~色の数は多いほど楽しい」TOKYO人権 第87号(令和2年9月10日発行)
https://www.tokyo-jinken.or.jp/site/tokyojinken/tj-87-interview.html - (2)コラム「アイヌ文化を伝える東京の若き紙芝居師(三橋 とらさん)」TOKYO人権 第76号(平成29年11月20日発行)
https://www.tokyo-jinken.or.jp/site/tokyojinken/tj-76-column.html - (3)特集記事「アイヌがアイヌとして生きていける社会へ」TOKYO人権 第63号(平成26年8月29日)
https://www.tokyo-jinken.or.jp/site/tokyojinken/tj-63-feature.html - (4)リレーTalk「アイヌの伝統文化で民族の誇りを取り戻す 魂に深く響くアイヌの五弦琴“トンコリ" (八幡 智子さん)」TOKYO人権 第49号(平成23年3月23日発行)
https://www.tokyo-jinken.or.jp/site/tokyojinken/tj-49-relay.html - (5)宇梶 静江さんインタビュー「アイヌ文化に輝きを:民族の誇りが息づく「古布絵」」TOKYO人権 第31号(平成18年9月25日発行)
https://www.tokyo-jinken.or.jp/site/tokyojinken/tj-31-feature1.html
注
(注1)東京都総務局人権部『みんなの人権』(2021年9月発行)。Webでもご覧いただけます。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/hokanko/upload/item/R3minnanojinken_1.pdf<外部リンク>(2022年1月31日閲覧)
(注2)国立アイヌ民族博物館ホームページ「よくある質問―アイヌの歴史・文化の基礎知識」を参照。特にQ12~Q14。(https://nam.go.jp/inquiry/<外部リンク> 2022年3月11日閲覧)
(注3)東京都政策報道室「人権に関する世論調査」(平成13年3月)
(注4)東京都総務局人権部「令和2年度 人権に関する都民の意識調査」(令和3年2月)
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/ishiki/index.html<外部リンク>(2022年1月31日閲覧)
(注5)「アイヌがアイヌとして生きていける社会へ」(公益財団法人東京都人権啓発センター発行「TOKYO人権」第63号、2014年8月29日)
Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Plaza. All rights reserved.